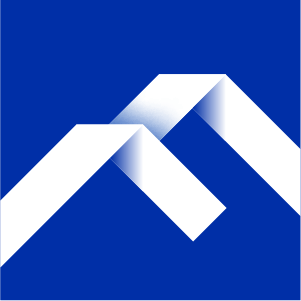原著者: Tiger Research
原文翻訳:AididiaoJP、Foresight News
要点
JPモルガン・チェースは、既存の金融秩序にブロックチェーン技術を重ね合わせ、パブリックブロックチェーン上で預金トークンの発行を開始した。
サークルは信託銀行のライセンスを申請し、テクノロジーに基づく新しい金融秩序の構築を目指している
2つのタイプの機関は、異なる方向から伝統的な金融を攻撃し、「双方向の収束」の傾向を形成している。
価値ポジショニングの曖昧さは、各社の競争優位性を弱める可能性があります。中核となる優位性を明確にし、バランスをとることが重要です。
オンチェーン金融インフラの新たな競争環境
ブロックチェーン技術は、世界の金融インフラの基本構造を再構築しつつあります。国際決済銀行(BIS)の最新レポートによると、2025年第2四半期時点で、世界のオンチェーン金融資産の規模は4.8兆米ドルを超え、年間成長率は65%を超えています。この変化の波の中で、従来の金融機関と暗号資産ネイティブ企業は、全く異なる発展の道筋を示しています。
伝統的な金融機関の代表であるJPモルガン・チェース
「ブロックチェーン+」という段階的な改革戦略を採用し、分散型台帳技術を既存の金融システムに組み込んでいます。同社のブロックチェーン部門であるOnyxは、280社以上の機関投資家にサービスを提供しており、年間取引額は6,000億米ドルに達しています。最新のJPMコインは、1日平均の決済額が120億米ドルを超えています。
暗号ネイティブ企業の代表であるCircle
USDCステーブルコインを通じて、ブロックチェーンを基盤とした金融ネットワークが構築されました。現在、USDCの流通量は540億米ドルに達し、16の主要なパブリックチェーンをサポートし、1日平均取引量は300万回を超えています。
2010 年代のフィンテック革命と比較すると、現在の競争には 3 つの大きな違いがあります。
競争の焦点はユーザーエクスペリエンスからインフラ再構築へ
技術的な深みはアプリケーション層からプロトコル層まで広がる
参加者は補完関係から直接的な競争関係に移行する
JPモルガン・チェース:伝統的な金融システムの枠組みにおける技術革新
JPモルガン・チェースは預金トークン「JPMD」の商標を申請した。
2025年6月、JPモルガン・チェースのブロックチェーン部門であるKinexysは、パブリックチェーンBase上で預金トークン「JPMD」の試験運用を開始しました。これまでJPモルガン・チェースは主にプライベートチェーンを通じてブロックチェーン技術を適用していましたが、今回はオープンネットワーク上で直接資産を発行し、流通をサポートすることで、従来の金融機関がパブリックチェーン上で直接金融サービスを運営し始めたことを示しています。
JPMDは、デジタル資産の特性と従来の預金機能を兼ね備えています。顧客が米ドルを預金すると、銀行は貸借対照表に預金を記録し、パブリックチェーン上に同額のJPMDを発行します。このトークンは、銀行預金に対する法的権利を保持したまま自由に流通できます。保有者は米ドルを1:1で交換でき、預金保険と利息収入を享受できます。既存のステーブルコインの収益は発行者に集中しますが、JPMDはユーザーに実質的な金融権利を与えることで、差別化された優位性を生み出します。
これらの特徴は、資産運用機関や投資家に非常に魅力的な実用価値を提供し、ある程度の法的リスクさえも無視できるほどです。例えば、ブラックロックのBUIDLファンドのようなオンチェーン資産がJPMDを償還決済手段として利用すれば、24時間いつでも償還が可能です。法定通貨に個別に交換する必要がある既存のステーブルコインと比較して、JPMDは即時の現金化をサポートし、預金保護と利息収入の機会を提供し、オンチェーン資産運用エコシステムにおいて大きな可能性を秘めています。
JPモルガン・チェースは、ステーブルコインによって形成された新たな資本フローと収益構造に対応するため、預金トークンを導入しました。テザーの年間収益は約130億米ドルで、サークルも国債などの安全資産の運用でかなりの収益を生み出しています。これらのモデルは従来の預金・貸出スプレッドとは異なりますが、顧客資金に基づいて収益を生み出す仕組みは、一部の銀行機能に似ています。
JPMDには制約もあります。既存の金融規制の枠組みに厳密に従った設計であるため、ブロックチェーンの完全な分散化とオープン性を実現することは困難であり、現在は機関投資家のみが利用できます。しかしながら、JPMDは、従来の金融機関が既存の安定性とコンプライアンス要件を維持しながらパブリックチェーン金融サービスに参入するための実用的な戦略であり、従来の金融とオンチェーンエコシステムの拡張と連携の代表的な事例とされています。
サークル:ブロックチェーンネイティブの金融再構築
Circleは、ステーブルコインUSDCを通じて、オンチェーン金融における重要な地位を確立しました。USDCは米ドルと1:1の比率でペッグされており、準備金は現金と短期米国債です。低手数料と即時決済といった技術的利点により、企業の決済や国際送金の実用的な代替手段となっています。USDCは、SWIFTネットワークの複雑なプロセスを必要とせずに24時間リアルタイムの送金をサポートし、企業が従来の金融インフラの限界を打破するのに役立ちます。
しかし、Circleの既存の事業構造は、BNYメロンがUSDC準備金を保有し、ブラックロックが資産運用を担うという、複数の制約に直面しています。この構造では、中核機能を外部機関に委託しています。Circleは金利収入を得ているものの、資産に対する実質的な支配力は限定的であり、現在の収益モデルは高金利環境に大きく依存しています。Circleは、長期的な持続可能性と収益の多様化を実現するために、より独立したインフラと運用権限を必要としています。
出典:サークル
Circleは2025年6月、米国通貨監督庁(OCC)に国家信託銀行ライセンスの取得を申請しました。この戦略的決定は、単なるコンプライアンス要件にとどまりません。業界はこれを、Circleがステーブルコイン発行者から機関投資家向け金融機関へと転換する動きと捉えています。信託銀行としてのアイデンティティ取得により、Circleは準備金の保管と運用を直接管理できるようになり、金融インフラの内部統制能力を強化するだけでなく、事業範囲の拡大に向けた条件も整えます。Circleは、機関投資家向けデジタル資産保管サービスの基盤を築くことになります。
暗号資産ネイティブ企業であるCircleは、制度的枠組みの中で持続可能な運用システムを確立するために戦略を調整しました。この変革には、既存の金融システムのルールと役割を受け入れることが必要であり、その代償として柔軟性の低下と規制負担の増加を伴います。今後取得できる具体的な許可は、政策の変更や規制解釈次第ですが、今回の試みは、オンチェーン金融構造が既存の制度的枠組みの中でどの程度確立されているかを測る重要なマイルストーンとなりました。
オンチェーン金融を支配するのは誰か?
JPモルガン・チェースのような伝統的な金融機関から、Circleのような暗号資産ネイティブ企業まで、様々なバックグラウンドを持つ参加者がオンチェーン金融エコシステムを積極的に構築しています。これは、かつてのフィンテック業界の競争環境を彷彿とさせます。テクノロジー企業は、決済や送金といったコア金融機能を社内で実装することで金融業界に参入し、金融機関はデジタルトランスフォーメーションを通じて利用者を拡大し、業務効率を向上させました。
鍵となるのは、この競争が両者の境界を打ち破っていることです。現在のオンチェーン金融分野でも同様の現象が生まれています。Circleは信託銀行ライセンスを申請することで準備金管理などのコア機能を直接担う一方、JPモルガン・チェースはパブリックチェーン上で預金トークンを発行し、オンチェーン資産運用事業を拡大しています。両者は異なる出発点から出発しながら、徐々に互いの戦略と分野を吸収し、新たな均衡点を模索しています。
この傾向は新たな機会をもたらす一方で、リスクも伴います。伝統的な金融機関がテクノロジー企業の柔軟性を無理やり模倣すると、既存のリスク管理システムと衝突する可能性があります。ドイツ銀行は「デジタルファースト」戦略を実行した際、レガシーシステムとの衝突により数十億ドルの損失を被りました。逆に、暗号資産ネイティブ企業が機関投資家による受け入れを過度に拡大すると、競争力を支える柔軟性を失う可能性があります。
オンチェーン金融競争の成否は、最終的には自社の基盤と優位性を明確に理解することにかかっています。企業は、自らの「不公平な優位性」に基づき、テクノロジーとシステムの有機的な統合を実現する必要があります。このバランス能力こそが、最終的な勝者を決定づけるのです。