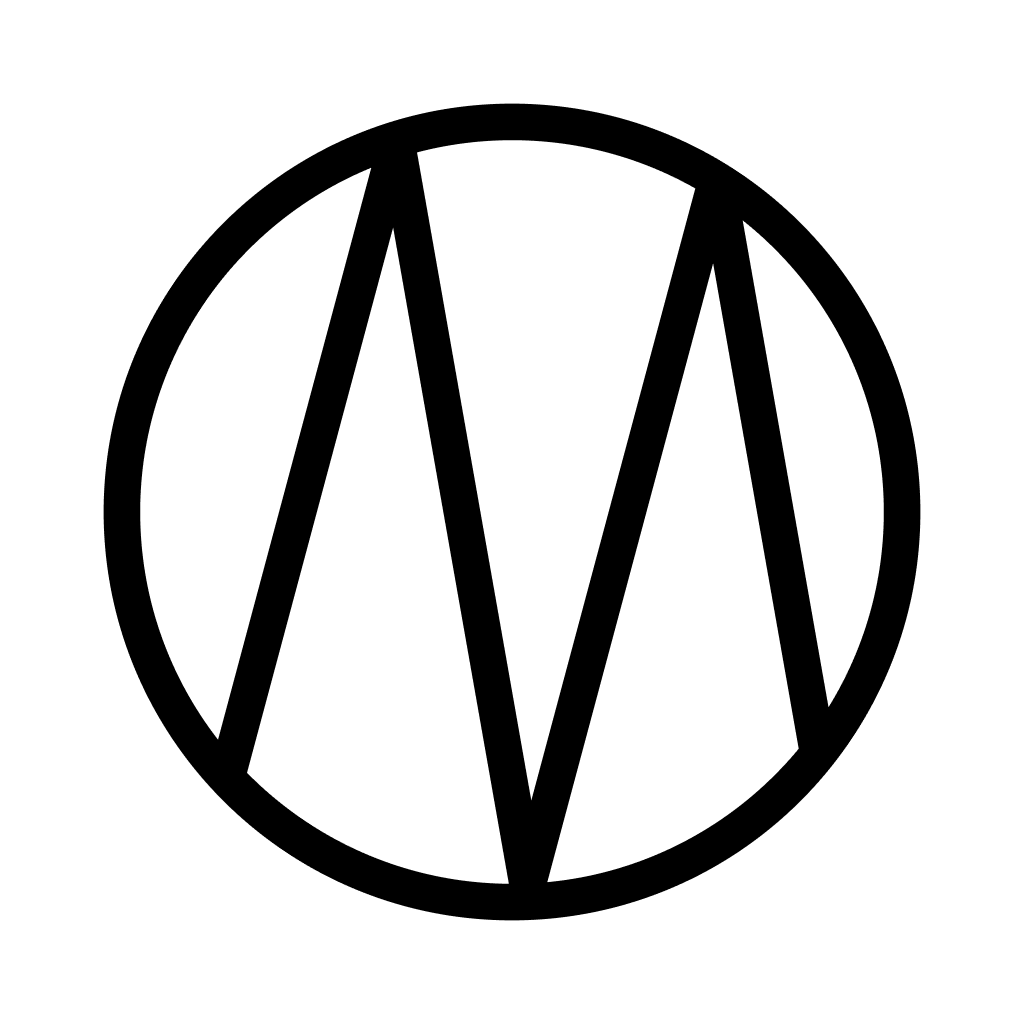取引所やカード発行会社の支援がなければ、Uカードは必然的にライフサイクルが短くなるだろう。
現在の決済システムは、質的変化の前の中間段階にあります。初期段階と比較すると、既存の製品は設計の詳細、ユーザビリティ、コンプライアンスパスにおいて大幅に改善されていますが、完全かつ持続可能なWeb3決済フレームワークの構築には、まだ長い道のりが残されています。それでもなお、この「未完成」な状態は、ここ数ヶ月、市場の議論の焦点の一つとなっています。
U カードは、現在の暗号通貨決済の最新形態として、本質的には「中間移行メカニズム」です。従来の Web2 チャージ カードの単純なコピーでも、新世代のオンチェーン ウォレットや決済チャネルの最終形態でもなく、オンチェーン決済シナリオとオフチェーン消費ニーズの間の現在の妥協の産物です。
U Cardは、オンチェーンアカウントとステーブルコイン残高を紐付け、さらにコンプライアンスに準拠した使いやすいオフチェーン消費インターフェースを補完することで、「Web2の使い慣れた体験」と「Web3の資産ロジック」を融合させたモデルを実際に実現しています。このモデルが過去6ヶ月で急速に注目を集めている理由は、一方では「オンチェーン資産を日常消費に活用できる」というユーザーの想像力が決して薄れていないこと、他方では、ステーブルコインがクロスボーダー取引やOTC決済といった従来の強力なシナリオから、Cエンドの小売やローカル決済システムへとさらに浸透しようとしていることを示しているからです。
U カードは、このトレンドの製品実装ポイントです。
Uカードは暗号資産決済を可能にしたことで、市場から大きな注目を集めました。Bybit、Infini、Bitgetなどが相次いで関連サービスを開始し、「暗号資産決済はすぐに普及するだろう」と人々は予想しました。しかし、現実には多くのプロジェクトが短期間で事業を縮小しており、特に取引所の実績や一流カード発行会社からの支援がないプロジェクトは、基本的に持続不可能です。
Uカードの事業モデルは、本質的に従来の金融システムの承認に大きく依存しており、コンプライアンスのプレッシャーとわずかな利益の間でかろうじて生き延びており、長期的な持続は困難です。
厳密に言えば、「Uカード」は安定した収益を生み出すビジネスモデルではなく、あくまで外部からの許可に依存したサービス形態です。
プロジェクト当事者は、決済を完了するためにカード組織や発行銀行などの多層的な金融仲介機関に依存する必要があり、自らはチェーンの末端の実行者でしかありません。
より大きな課題は、Uカードの運営コストが非常に高く、実質的に赤字事業となっていることです。プロジェクト側は取引所のような安定した手数料収入を得ることも、一流カード発行会社のような発言権を持つこともできず、ユーザーからのサービス圧力に耐えなければなりません。
問題の核心は、プロジェクト側が常に「仲介者の仲介者」の役割にとどまっている限り、ライセンスエコシステムの底辺で受動的に活動することしかできないことです。この状況を変えるには、二つの道があります。もし現状打破できないのであれば、アカウントシステムに参加し、暗号資産業界をアカウントシステムのエコシステムとして繋ぎ、コンプライアンスメカニズムに発言権を持ち、決済システムの一部として発展していくか、あるいは自ら事業を立ち上げ、米国ステーブルコイン法案の更なる改善を待ち、現在の煩雑で非効率な決済システムを回避し、米ドルの地位低下時に米ドルステーブルコインがもたらす新たな出口を受け入れるかです。
ウォレットや取引所にとって、Uカードは収益源というよりは、ユーザーの定着率を高めるための補助的な機能です。Bybitのような取引所にとって、Uカード事業が収益性に欠けるとしても、ユーザー数の増加や資産運用のスケールアップに繋がる可能性があります。しかし、トラフィック流入や金融インフラ構築の経験が不足しているWeb3スタートアップ企業にとって、補助金やスケールアップによって持続可能なUカードプロジェクトを疲弊させようとするのは、檻の中に獣を閉じ込めるようなものです。
暗号通貨決済の次のステップは、地下銀行か、それともチェーン上の「新しい」銀行か?
ここまでで、まず結論を出していきましょう。暗号通貨決済を悩ませているのは、従来の金融決済システムです。しかし、暗号通貨決済とは何でしょうか?市場には様々な意見があります。日常生活におけるスキャン決済の完全な模倣なのか、それとも匿名ネットワークに新たな意味を見出すための新たな方法なのか。後者にとって、決済の意味は送金ではなく沈殿です。したがって、このセマンティクスにおいて、決済の本質は清算ではなく循環であり、これはブロックチェーンの発展とともに暗黒の森の中で急速に成長した産業です。
潮汕人やインド、パキスタンの地下銀行を例に挙げてみましょう。彼らは、人間関係、信頼、そして資産循環を基盤としたデジタルエコシステムを構築しています。しかし、たとえ「潮汕人」になりたくても、「山東人」の習慣に完全に適応するのは困難です。
潮汕型デジタル銀行とは何か?その本質は信頼である。資金の循環は「信頼」に依存し、決済遅延による資産の沈殿と循環も「信頼」に依存し、互いをよく知ることで生まれる「信頼」と、裏切りによる社会的死のリスクによって形成される「信頼」によって形成される。潮汕型デジタル銀行は、知人からの紹介を必須とし、見知らぬ人が利用する可能性を排除している。そこには、誰もが目に見えない共同責任の仕組みがある。紹介した人が裏切らないようにするだけでなく、紹介した人の次の人も裏切らないようにしなければならない。そうでなければ、失敗はすべてのラインを根こそぎにしてしまう。
このようなメカニズムでは、支払いはもはや1対1の関係ではなく、そのような価値ネットワーク内で継続的に循環する1対多対1の形式になります。
資金が流入すると、彼らは決済だけでなく、信頼獲得にもゲームに参加する。不払い資金が継続的に流入すると、資金は預金となる。銀行に「潮汕人」が増えれば増えるほど、決済は遅いが高頻度のソーシャル決済ネットワークへと発展する。価値の継続的な循環と無限の流れは、豊かな利益をもたらすだろう。
実際、「デジタル銀行」という閉鎖的なエコシステム構造は長年にわたりチェーン上で稼働しており、一部の資金のグレーゾーン流通という問題を解決してきたものの、「暗号化決済」をニッチ市場から主流へと押し上げることはできていない。むしろ、真にグローバルな潜在力を持ち、ユーザーエンドに徐々に近づいているのは、米ドルステーブルコインを核としたコンプライアンスネットワーク上に構築されたオンチェーン決済システムである。
地下銀行型のオンチェーン構造が実際には長らく存在していたという事実に立ち返りましょう。東南アジアのグレーマーケットの裁定取引組織であれ、ロシア軍がUSDTを介して行った国際決済であれ、デジタル資産は既に伝統的な金融システムを迂回し、資本の自由な流れを実現する成熟した手段を有していました。
特に、Tronネットワークの台頭はこの論理を反映しています。TRM LabsやChainArgosといったオンチェーンセキュリティ企業のレポートによると、2023年から2024年にかけて、違法なオンチェーン資金フローの40%以上がTronネットワーク上で発生し、その半分以上がUSDTを通じて行われました。
これらの資金は取引所には流入せず、OTCヘッジ、ウォレットの「アイランドホッピング」、DEXの迂回など、地下銀行と同様の「ミラーリリース」操作を完了しました。この運用形態は、潮汕の人々が構築した海外資本ネットワークと非常に類似しています。決済レイヤーのファイナリティを追求するのではなく、分散型信頼チェーンとクロスボーダーネットワークシステムに依存して流動性を確保しています。しかし問題は、このようなオンチェーン「デジタルバンク」が5年も稼働しているにもかかわらず、なぜ暗号化決済の普及が未だに見られないのかということです。発展を続ける必要があるのでしょうか、それとも、その熱狂は私たちとは無関係なのでしょうか?
根本的な理由は、この種のモデルが一般ユーザー向けに設計されていないことです。このモデルは「より多くの人々に暗号通貨で支払いをしてもらう方法」という問題を解決するのではなく、「少数の人々に追跡不可能な暗号通貨による支払いをしてもらう方法」という問題を解決します。
その出発点は、接続ではなくバイパスです。法的保護を必要とするユーザー グループではなく、規制の対象になりたくないシナリオに役立ちます。
潮汕金融ネットワークは、タイ、フィリピン、香港の間で効率的な「家族送金システム」を構築できますが、この構造がグローバルに拡張可能なインフラへと転換できるわけではありません。これは効率的なローカルエリアネットワークのようなもので、限界領域では非常に柔軟ですが、グローバル市場の既存の決済システムとの接続は困難です。
システムの観点から見ると、「資本が流出しにくい」ことは確かにプラットフォームのTVLを増加させ、DeFiエコシステムの資本利用率を向上させることができますが、決済システムの観点から見ると、真にスケーラブルなシステムには、資金が「入ってくるが出ない」のではなく、自由に「出入りできる」ことが必要です。
TONの紅包システムや各種オンチェーンポイントアカウントは、決済というエントリー行動を沈殿に転換するという共通の目的を持っています。これはWeb2時代の「余額宝(Yuebao)」のロジックに似ています。この沈殿モデルは確かに商業的価値を持っていますが、生態系の壁を突破することはできません。ユーザーはTONウォレット内の資産を自由にクロスボーダー決済、加盟店決済、POSレジに利用できず、現実世界のアカウントシステムとの安定したマッピングも得られません。「潮汕人」はマッピングを必要としないかもしれませんが、アメリカの「潮汕方言」で同じことをすることはできません。
言い換えれば、この「裏庭循環」モデルはインフラではなく、生態系の自己強化メカニズムである。閉鎖的なシステムにおける資金の利用を強化することは重要であるものの、グローバルサービスとしての「決済」の基本ロジックを構成するものではない。
Web3決済を「ダークウェブ」から「メインウェブ」へと押し上げた真の原動力は、米国の政策レベルでのステーブルコイン決済ネットワークへの支援です。米国財務省が2024年にGENIUS法を正式に推進し、議会が決済の透明性確保のためのステーブルコイン法案を可決したことで、ステーブルコインは初めて「戦略的決済インフラ」という政策的位置づけを受けました。
Circle、Paxos、Stripe、Visa、Mastercardなどのフィンテック企業は、国際決済、加盟店獲得、プラットフォーム決済における米ドル建てステーブルコインの応用拡大を急速に推進しています。Visaが2024年初頭に発表したデータによると、30以上のグローバル決済機関がUSDCをクロスボーダー決済資産として導入しており、USDCとPYUSDの発行・利用シーンもリテール分野に浸透し始めています。
これらは仮想経済における循環や沈殿ではなく、現実の財・サービス間の資金の流れであり、法的保護と監査コンプライアンスを備えた決済行為です。対照的に、TONエコシステムにおけるトークン決済や一部ウォレットの「コードスキャン決済」機能は、企業の財務報告システム、多国籍電子商取引プラットフォーム、信用ネットワークに真に組み込まれる前は、グローバルな決済基準ではなく、依然として閉鎖システム内のローカル機能に過ぎません。
「デジタルバンク」のメカニズム設計が刺激的であることは否定できない。意図やアカウントの抽象化といった提案は、確かに従来のオンチェーン決済を「マシンツーマシン」の送金から「人間の意図主導型」の資金調整へと進化させている。これは、従来の地下銀行が「関係性に基づく強固な信頼」メカニズムを応用している点と、ある種の哲学的共鳴点を持つ。しかし、体系的な決済構造は、漠然とした社会的信頼とローカルな流通ロジックだけでは構築できない。最終的には監督管理と連携し、ユーザーの身元、取引プロセス、資金源を追跡できるようにする必要がある。
同時に、暗号化決済の発展方向をよりマクロ的な視点から捉える必要がある。米ドルの国際通貨地位が構造的な課題に直面する中、米国の財政・通貨システムは「米ドル+米ドル・ステーブルコイン」という新たな双軌道通貨システムの構築を模索している。人民元決済の拡大をヘッジするため、ユーロ/金決済を活用した新興市場の動向に対応するため、あるいは中東、東南アジアなどの地域における自国の金融影響力を安定させるためなど、ステーブルコインはもはや周辺的な金融イノベーションではなく、国際金融競争において米国が積極的に展開する戦略ツールとなっている。
このため、過去2年間、議会の立法から財務省の指導、従来型銀行の参加から決済ネットワークへの組み込みに至るまで、米ドル建てステーブルコインの推進が全面的に加速し、ソブリン通貨とソブリン規制の枠組みに深く統合されつつあるのが見受けられる。
そこで疑問となるのは、デジタルマネーハウスの決済モデルはそのような戦略的なシステムを支えることができるのか、ということだ。もちろん、それは不可能だ。アンダーグラウンドマネーハウスモデルの本質は規制回避にあるが、米国は規制を組み込んだグローバル金融ネットワークの構築を目指している。デジタルマネーハウスはコミュニティの信頼とグレーゾーンの裁定取引に依存しているが、米ドルのステーブルコインシステムは、規制に準拠した金融機関と規制ライセンスチェーンの上に構築されなければならない。
米国財務省が、KYC非対応ウォレット、匿名ブリッジ、そしてOTC取引に依存する資金調達ネットワークに重要な決済インフラを委譲するとは想像しがたい。デジタル銀行は限界領域における流通問題を解決することはできるが、国家レベルの主権国家的な通貨統治構造を形成することはできない。ステーブルコインこそが、この役割を担っていると言えるだろう。
つまり、暗号資産業界の未来は、グレーゾーンの業界との共生関係にはならないということです。暗号資産業界がまだ成熟していなかった時代には、グレーゾーンの脇役としての役割を担っていましたが、ビットコインETFの承認により、暗号資産業界は新たなサイクルに入り、伝統的な金融との完全な統合と相互に絡み合う未来へと向かうのです。
JPモルガン・チェースによるJPMコインの発行、ブラックロックによるBUIDLファンドの展開、VisaによるUSDCの統合、Stripeによるオンチェーン決済へのアクセス、Circleによる世界各国の中央銀行との政策連携など、これらの取り組みはすべて、従来の金融がオンチェーン世界への進出を加速させていることを示しています。そして、その基準はコンプライアンス、透明性、そして規制という明確なものです。この基準は、当然のことながら、地下マネーハウスの論理的拡張を排除しており、暗号化決済の主流としての「デジタルマネーハウス」モデルの根本的な限界となっています。
Web3決済の真の未来は、米ドル建てステーブルコインとコンプライアンス決済チャネルを基盤として構築されるネットワークです。分散化の開放性を実現するだけでなく、既存の法定通貨システムの信用基盤も活用できます。資金の自由な出入りを可能にしますが、沈殿を盲目的に信じることはありません。アイデンティティの抽象化を重視しますが、監督を逃れることはありません。ユーザーの意図を統合しますが、法的境界を逸脱することはありません。このシステムでは、資金はWeb3の世界に流入するだけでなく、自由に流出することができます。サービスチェーンにおける金融活動にサービスを提供するだけでなく、グローバルな商品・サービスの交換にも組み込まれています。
デジタル銀行は、目に見えず流れに沿って移動する水のような存在です。一滴の雨が流れ込むと、海へと変化します。暗号化決済の次の段階は、光のような存在であるべきです。光は互いに溶け合いながらも、独自の起源を持ちます。源泉を辿れば、明確な帰路が見つかります。貪欲に貪りつくのではなく、光を照らすことに重点を置くのです。
Movemakerについて
Movemakerは、Aptos Foundationによって認可され、AnkaaとBlockBoosterが共同で立ち上げた初の公式コミュニティ組織であり、Aptos中国エコシステムの構築と発展の促進に重点を置いています。中国地域におけるAptosの公式代表として、Movemakerは開発者、ユーザー、資本、そして多くのエコシステムパートナーを結びつけることで、多様性に富み、オープンで繁栄するAptosエコシステムの構築に尽力しています。
免責事項:
この記事/ブログは情報提供のみを目的としており、著者の個人的な意見を表したものであり、必ずしもMovemakerの立場を代表するものではありません。この記事は、(i)投資助言または投資推奨、(ii)デジタル資産の売買または保有の申し出または勧誘、(iii)財務、会計、法律、または税務に関するアドバイスを提供することを意図したものではありません。ステーブルコインやNFTを含むデジタル資産の保有は非常にリスクが高く、価格が変動して価値がなくなる可能性があります。ご自身の財務状況に基づいて、デジタル資産の取引または保有が適切かどうかを慎重に検討する必要があります。具体的な状況についてご質問がある場合は、法律、税務、または投資アドバイザーにご相談ください。この記事で提供される情報(市場データおよび統計情報を含む)は、一般的な情報提供のみを目的としています。これらのデータおよびチャートの作成には合理的な注意が払われていますが、そこに表明された事実上の誤りまたは省略については一切責任を負いません。